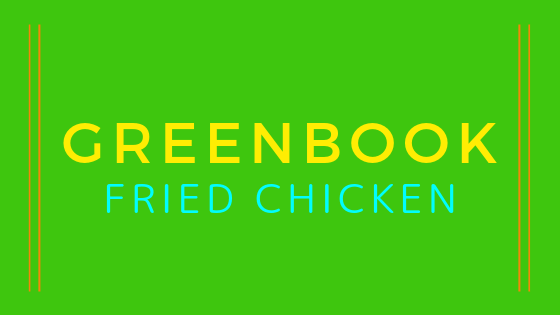
3月1日に今年のアカデミー賞受賞作「グリーンブック」が公開されたものの、ファーストデーは博多でIMAXとドルビーシネマのはしごをしたため、まだ見に行けていない。
はやく見たいなあと思いつつTwitterを見ていたら、「グリーンブック」に関する話題で、こんなツイートがあった。
黒人とフライドチキンの関係性がわかる2つのコンテンツ
映画『グリーンブック』に併せて、Netflix『アグリー・デリシャス』の第6回、フライドチキン回を見ておくといいと思う。カジュアルな食べ物であるフライドチキンだが、アメリカ社会では人種と根強く結びついてしまい、非常にセンシティブな意味を背負う食べ物でもあると知り、なかなか衝撃を受けた。 pic.twitter.com/sS2f1bacHF
— ぬまがさワタリ@『絶滅どうぶつ図鑑』&福岡マリンワールドで1月よりコラボ展! (@numagasa) 2019年3月2日
「グリーンブック」の予告編を見たら、フライドチキンを車で食べるシーンがある。そのシーンに含まれるニュアンスを理解するには、Netflixで見れるドキュメンタリー、「アグリー・デリシャス」のフライドチキン回がおすすめというツイート。黒人とフライドチキンの関係性についてわかりやすく説明されているようだ。
あとこんなツイートもあった。
フライドチキンについては こちらの新書でも 興味深く しかも読みやすくていいんじゃないかしら pic.twitter.com/6fEQuBkQU0
— アニマ・ムンディ (@animamundi_) 2019年3月2日
黒人とフライドチキンの関係を知るにはこの本もおすすめというツイート。
せっかくなので「グリーンブック」見る前にこのツイートで紹介されている「被差別の食卓」、読んでみました。
あと今Netflixにお試し入会しているので、読んだ後に「アグリー・デリシャス」第6回も見ました。なんで今回はそのことについて書いていきます。
まず最初に読んだ「被差別の食卓」について。
上原善広著「被差別の食卓」
大阪のある被差別部落では、そこでしか食べられない料理がある。あぶらかす、さいぼし…。一般地区の人々が見向きもしない余り物を食べやすいように工夫した独自の食文化である。その“むら”で生まれ育った著者は、やがて世界各地にある被差別の民が作り上げた食を味わうための旅に出た。フライドチキン、フェジョアーダ、ハリネズミ料理―。単に「おいしい」だけではすまされない“魂の料理”がそこにあった。
あぶらかすと菜っぱの煮物が子供の頃好物だったノンフィクションライターの上原善広さんが、日本のあぶらかすのような“むら”独特の「ソウルフード」を取材した旅の記録です。
思ってたよりもめっちゃ読みやすい本でした。
どんくらい読みやすいかというと、こんなわかりやすいうえ情報も詰め込まれた文章書けるようになりたいなあとブログやってる身として思うくらい、めっちゃ読みやすいです。
読みやすいのに読者の想定偏差値が低くていらいらするというわけではなく、なのに気軽に読める絶妙な難易度。本をあまり読まない人でも難なく読めて、全然読んでて苦にならない。上原さんの本、これからチェックしようかなと思えるレベルでした。
で、内容としては、1章がアメリカに住む黒人のソウルフードについて書かれていて、次にブラジル、ブルガリア・イラク、ネパール、日本と続きます。
アメリカについて書かれている1章はまずチトリングス(豚モツ煮)、フライドチキン、キャットフィッシュ(なまず)フライ、ガンボなどといったソウルフードを扱っており、上原さんが現地で食したり話を聞いたりするといった内容。そしてそういった地域で旅をすることによってその土地特有の差別の実態も垣間見ることになる。
そこで著者は、食べにくい内臓を食べやすいようにカリカリに揚げた「あぶらかす」と同じように、フライドチキンは白人が捨てる食べにくい部位を長時間揚げることによって、骨を柔らかくし、骨ごと食べれるようにしたソウルフードだということを知る。
そういえばケンタッキー・フライド・チキンの肉にも、焼いただけだと食べづらそうな、えぐみの強いものがついてくるやつもある。あと骨の付け根の軟骨も食べやすくなっている。こういった部分もまるごと食べれるよう編み出された食べ方なのだ。
こういった、捨てるような部分を食べれるようにした被差別ならではのグルメを、いろいろな地域ごとに次々と紹介していく本だ。
そもそも僕は「ソウルフード」という言葉に「むらの食事」というニュアンスが強く含まれていることを知らなかったし、郷土料理的なものだろうと思っていたのでそれだけでも衝撃で、読んでいていろいろと発見のある本でした。
あとアメリカ以外のところだと、ブルガリアに住むロマの話とかも面白かったです。ハリネズミを日常的に食べているという驚きの食生活について知ることができました。
Netflixドキュメンタリー「アグリー・デリシャス」第6回
続いて、お試し体験中のNetflixにて「アグリー・デリシャス」第6回を見る。1〜5はまだ見ていないですが非常に良く出来たドキュメンタリーでした。
妥協を許さないスターシェフ、デイビッド・チャンが友人たちとともに、世界中で愛されている定番メニューの数々に舌鼓を打ちながら、食と文化を掘り下げていく。
アメリカで製作されたNetflixオリジナルドキュメンタリーなのに、いきなり日本が舞台。コンビニ(ローソン)に入って物色、日本一の乳酸菌飲料「カルピス」を紹介。ピスという言葉がついた液体は英語圏だとちょっとやばい意味になる。レジに進むとホットスナックコーナーでからあげを発見。今回のテーマはフライドチキンだ。
ナッシュビルのフライドチキン店や、フライドチキンから影響を受けた創作料理を出す日本の料理店が出てきたりする。フライドチキンという食べ物が世界でどのように変化しているのかが語られ、アメリカでフライドチキンを語るには避けて通れないチキンとステレオタイプの話題に移る。
黒人のコメディアンがチキンの話題で笑いをとるスタンダップコメディとコントの映像が流れ、黒人差別とチキンがなぜ結びついているのかが説明される。
チキンは黒人奴隷でも飼えただとか、主人のために黒人がチキンを揚げていたとか、チキンで起業した黒人の話などが積み重なり、黒人を象徴する食べ物になった過程が語られ、非常に入り組んだ歴史を、簡潔にわかりやすく説明されている。
また、全体的にオリジナリティあふれるフライドチキンが出てくるので、この作品を見てもチキンが食べたくなります。マクドナルドのチキンナゲットのルーツも知ることもできる、非常に良く出来たドキュメンタリーでした。
まとめ
最近Netflixがない生活なんて考えられないみたいな感じになっててちょっとやばいです。お試しが終わったら一時退会する予定だったんですが。こういった良質なコンテンツがたくさんあるからやめられないかも。ドキュメンタリーの方も、本の方も、2つともおすすめです。目からウロコが落ちるような、知的好奇心が刺激されるコンテンツでした。
「グリーンブック」は金曜日に「運び屋」と一緒に見ようと思います。作品本編については見てから書く予定です。では。















